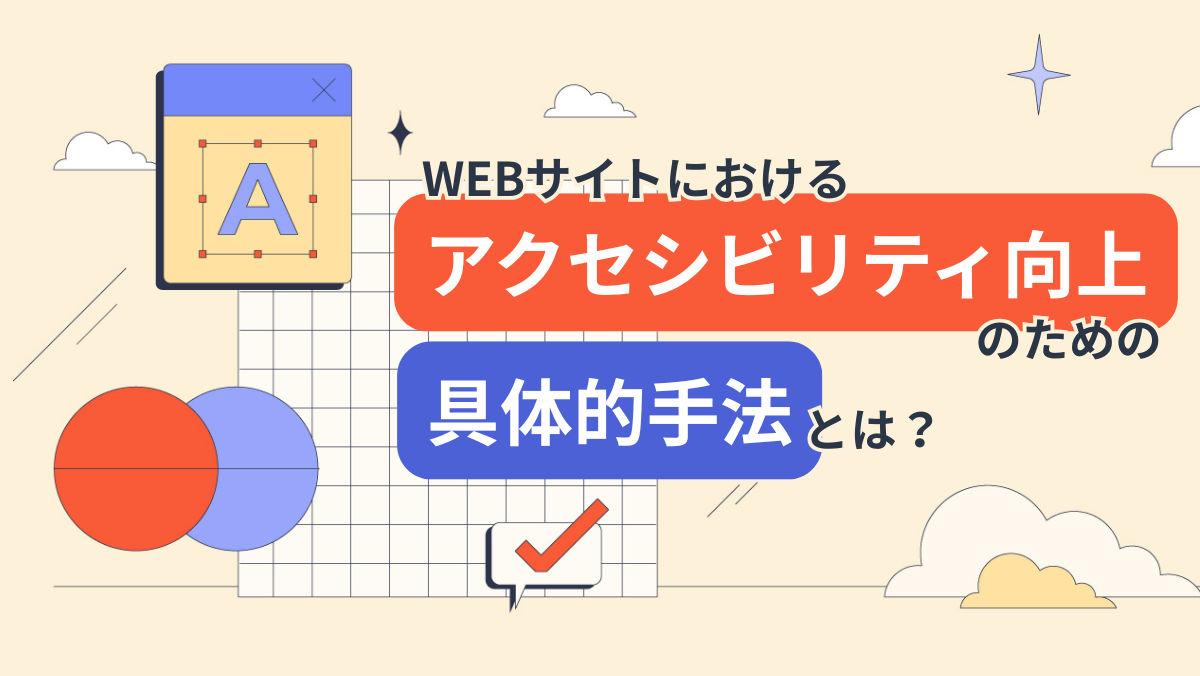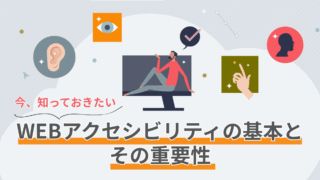インターネットの普及により、WEBサイトはあらゆる人々にとって情報への入口となりました。こうした中で、誰もがストレスなくWEBサイトを利用できる環境を整えること、すなわち「WEBアクセシビリティ」の重要性がますます高まっています。
WEBアクセシビリティとは、障害の有無、年齢、使用デバイスや通信環境に関係なく、すべての人が公平に情報へアクセスできる状態を指します。これは特定のユーザーのための配慮ではなく、あらゆる利用者にとって「使いやすい」ことを追求する、現代のWEB設計における基本姿勢です。
前回の記事(WEBアクセシビリティとは何か?その背景と基本ルール)では、基礎的な考え方や法律、メリットについて解説しました。今回はそれを踏まえ、WEBアクセシビリティ向上に向けた実践的な取り組みについて、導入の流れから具体的な設計・運用、社内体制までを詳しく解説します。
<関連記事>
▼あわせて読みたい
アクセシビリティ向上のための導入ステップ
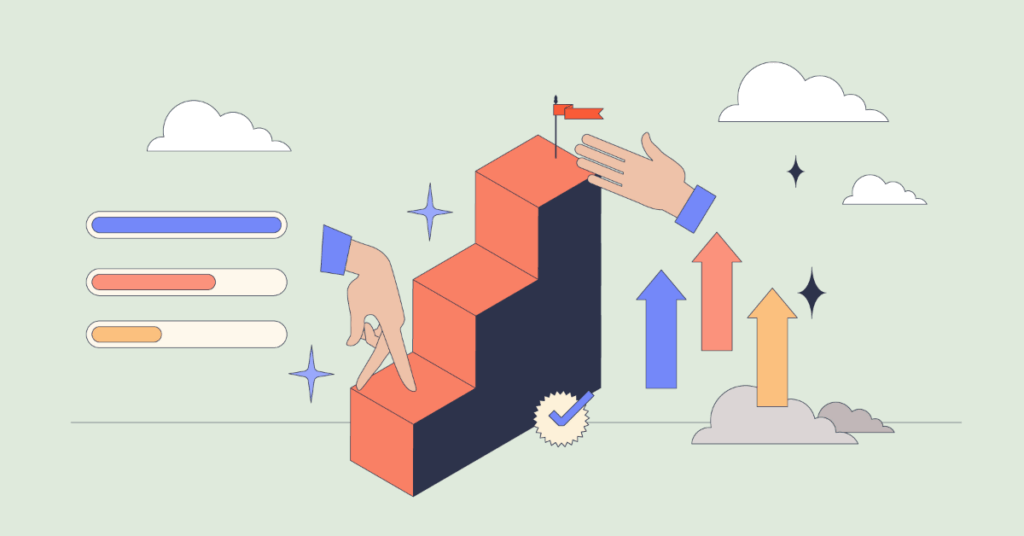
WEBアクセシビリティへの対応は、感覚的な取り組みではなく、段階的なステップでの計画と実施が効果的です。以下の流れで導入を進めていきましょう。
現状分析
まずは現状のWEBサイトがどれだけ多様なユーザーにとって使いやすい状態かを把握することが重要です。
例えば自社のサイトのアクセシビリティをチェックする場合、チェックリストや自動診断ツール(後述)を活用し、JIS X 8341-3:2016の基準(適合レベルAAを目安)に照らして課題を洗い出していきます。
▼主な確認ポイントと対応の具体例
- 情報の伝わりやすさ
- 例:会社案内がPDFしかない → スマホでも読みやすいHTML形式も用意する
- 例:画像に説明がない → alt属性で内容を補足する(スクリーンリーダー利用者・画像表示がオフの人にも有効)
- 色や視認性への配慮
- 例:ボタンが「赤=危険」「緑=安全」と色だけで区別されている → ラベルやアイコン、形でも状態を明示(色覚多様性、高齢者配慮)
- 操作のしやすさ
- 例:マウス操作前提のUI → キーボードや音声操作でも使える設計に
- 例:スマホでメニューが小さく押しにくい → タップしやすいサイズに変更
- 音声・映像コンテンツの対応
- 例:動画に字幕がない → 音を出せない環境の人のためにキャプションを追加
- 例:ナレーション付きスライド → 文字情報の補足やスクリプトも提供
このように、「誰でも・どんな状況でも使いやすいか」という視点で現状を見直すことが、WEBアクセシビリティ改善の第一歩です。
なお、WEBアクセシビリティの評価基準として、日本では「JIS X 8341-3:2016」が広く活用されています。
改善方針を検討する際は、全体の要件を一覧できる「対応のための早見表(WAIC公式)」を活用することで、対応範囲の見通しが立てやすくなります。
JIS X 8341-3:2016 対応のための早見表(WAIC公式)
目標設定
現状の課題が見えてきたら、次は「どこをどう改善するか」を明確にします。
このステップでは、具体的で測定可能な目標を立てることがカギになります。
たとえば、
- 視覚に制限のあるユーザーが、サイト内検索をスムーズに使えるようにナビゲーション構造を見直す
- 色覚多様性に配慮し、ボタンやリンクのコントラスト比をJISの基準に適合させる
- 画像すべてに適切な代替テキストを設定する
といったように、誰のために、何をどうするかを具体化しておくことで、社内での合意形成がしやすくなり、効果の振り返りも可能になります。
実施計画の策定
目標が定まったら、実現するための道筋を描くフェーズです。
対応すべき項目の優先順位を整理し、スケジュールや担当者、予算、必要なスキルなどを検討します。
すべてを一度に完璧に対応しようとするのではなく、たとえば
- 「まずはTOPページと主要導線のアクセシビリティを強化する」
- 「その後、問い合わせフォームや採用ページも順次対応していく」
といった段階的なアプローチがおすすめです。
また、内製・外注どちらが最適か、社内体制の見直しも含めて検討しましょう。
社内共有と啓発
アクセシビリティは、一部の担当者だけが頑張るものではなく、全社的な意識づけが成功の鍵です。
特に、デザイン・コーディング・コンテンツ編集・マーケティングなど、各分野での共通理解が重要になります。
- なぜアクセシビリティが必要なのか
- どんな工夫が誰に役立つのか
- 自分の仕事にどう関わるのか
を共有することで、「言われたからやる」ではなく「必要だから取り組む」空気が社内に根づいていきます。
このように「現状把握→目標設定→施策計画→組織体制構築」という流れを明確にすることで、社内の理解と共感を得やすくなります。
WEBデザインの工夫
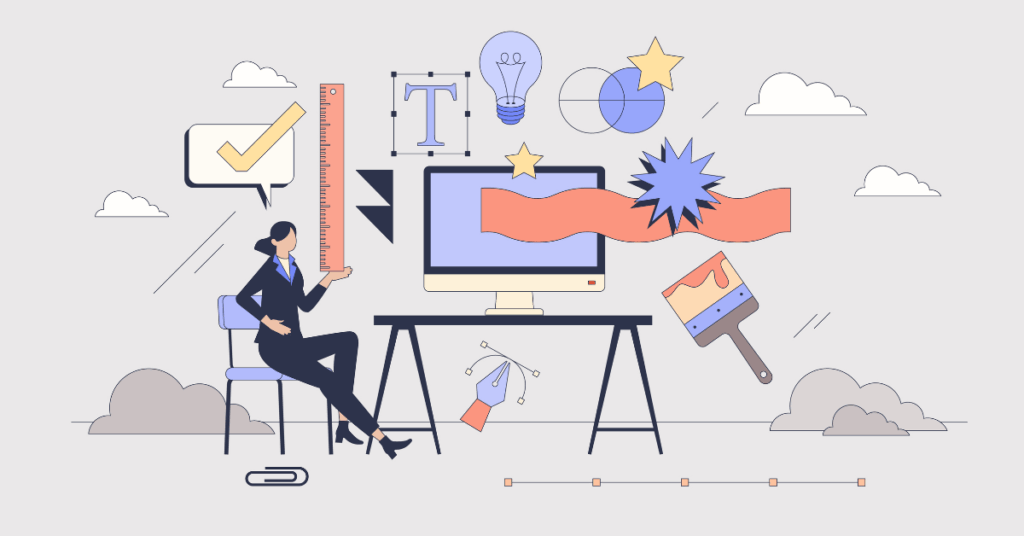
WEBアクセシビリティを確保するためには、デザイン段階での配慮が欠かせません。見た目の美しさやブランド表現だけでなく、「誰でも読みやすく、直感的に操作しやすい」ことを意識することが重要です。
ここでは基本的な工夫の一例を紹介します。
色彩とコントラスト
- テキストと背景のコントラスト比は最低4.5:1を目安に(小さな文字や重要な情報は7:1が望ましいとされています)。コントラスト比は、WebAIMのContrast Checkerなどのツールを使えば簡単に確認できます。
- 色だけで意味を伝えるのではなく、アイコンやラベル、文字による補足表現を併用するようにします。
フォントと文字周りの設計
- 一般的に視認性が高いとされるサンセリフ系フォント(Arial、Helveticaなど)を使用。
- 行間や文字間(カーニング)を適切に設計することで、読みやすさが大きく向上します。
レイアウトとナビゲーション
- サイト構造は、論理的な階層と見出しタグ(h1〜h3など)の正しい活用を基本にします。
- ボタンやメニューは視認しやすく、タップしやすいサイズと十分な間隔を確保。
- レスポンシブ対応により、モバイル端末からでも快適に閲覧できるように設計します。
これらのデザイン上の工夫は、色覚に多様性のある方や高齢のユーザー、一時的に画面を見づらい状況にある方にも配慮した、使いやすいWEB体験を提供することにつながります。
さらに詳しい事例や実践的な設計ポイントについては、デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」も参考になります。
テクノロジーの活用
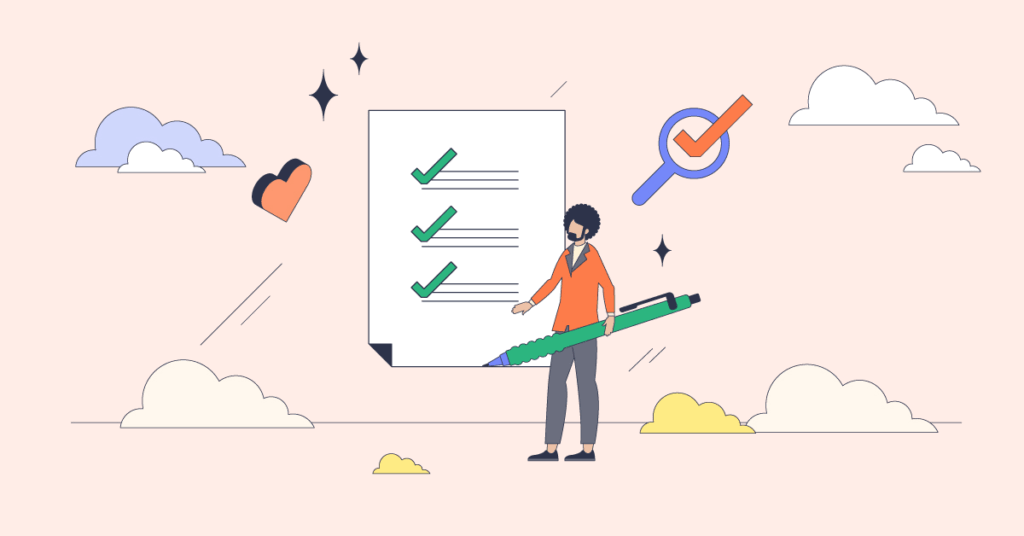
WEBアクセシビリティは、手作業によるチェックに加えて、専用ツールを活用した継続的な評価と改善が不可欠です。以下に、代表的なツールとその特徴を紹介します。
自動チェックツール
miChecker(総務省提供)
IS X 8341-3:2016に準拠した無料のアクセシビリティ評価ツール。日本語サイトに特化しており、自治体・官公庁でも広く利用されています。
→ miChecker公式サイト
axe DevTools(Deque Systems)
Google ChromeやFirefoxで使える無料のブラウザ拡張機能。HTMLやARIA属性など、コードレベルでの問題点を即座に検出します。
WAVE(WebAIM)
入力したURLに対して視覚的なフィードバックを表示。初心者にも使いやすく、軽微な修正の指針に最適です。
→WAVE
Lighthouse(Google)
Google Chromeに搭載されている開発者ツールの1つで、アクセシビリティを含む総合的なパフォーマンス評価が可能です。
UI・HTML生成支援ツール
- ユニウェブやSiteimproveなどの商用サービスでは、アクセシビリティ基準に沿ったUIコンポーネントの導入やチェックが容易になります。
- Headless CMSやノーコードツール(例:STUDIO、Webflow)でも、最近はアクセシビリティ対応済のテーマやテンプレートが増えています。
評価と改善のサイクル

アクセシビリティ対応は「一度やって終わり」ではありません。定期的な評価→改善→再評価のループが求められます。
ユーザビリティテストの導入
- 障害当事者を含むユーザーにテストを依頼し、実際の操作体験から問題を洗い出す。
- サイト内検索、購入フォーム、ページ移動などの主要動線での操作性を重点確認。
定量的評価ツールの利用
- Google Lighthouse
- アクセシビリティだけでなく、パフォーマンスやSEOも含めた総合評価。
- レポート化・社内共有
- 数値だけでなく、実行可能な改善アクションとして整理し、定例化すると効果的。
ユーザーからのフィードバック窓口
- サイトに「ご意見フォーム」や「アクセシビリティに関するご相談窓口」を設置。
- 送られた意見は開発・運営サイドと共有し、改善に活かす体制を。
社内教育と意識向上

アクセシビリティの取り組みは、一人の担当者では完結しません。全社的な意識の定着と継続的なナレッジ共有が求められます。
以下の施策を通じて、従業員の知識と関心を高めていきましょう。
アクセシビリティ研修の実施
- 基礎知識の提供
- アクセシビリティに関する基本的な知識を学ぶ研修を定期的に開催します。法律やガイドラインについても触れることで背景理解を深めます。
- 実践的なワークショップ
- 実際のケーススタディを基にしたワークショップを開催し、参加者が自サイトに即した具体的なアイデアを考える機会を設けます。
ナレッジシェアの促進
- アクセシビリティの専用グループを作成
- 社内でアクセシビリティに特化した情報を共有するためのプラットフォームを設立し、最新情報やノウハウを常にアップデートします。
- 成功事例の共有
- 良い取り組みを行ったチームの成功事例を全社的に紹介し、他部門への刺激材料とします。
継続的な意識向上
- イントラネットでの情報発信
- 社内コミュニケーションツールやイントラネットに、アクセシビリティに関するコンテンツ(ブログや学習資料)を積極的に掲載します。
- フィードバックの文化を育成
- アクセシビリティに関する意見や懸念を気軽に伝えられる環境を整え、全社員が参加できる取り組みを行います。
こうした社内教育や意識向上の施策は、組織全体の力を結集することでWEBサイトのアクセシビリティ向上を実現します。
まとめ
WEBアクセシビリティの向上は、あらゆる人にとって使いやすいWEB体験を実現すると同時に、企業の信頼性やブランド価値を高める重要な取り組みです。
導入ステップを明確にし、デザインや技術、評価・運用・社内文化までをトータルで考えることで、誰もが安心して利用できるサイトが実現します。
アクセシビリティは「特別な対応」ではなく、すべてのユーザーの利便性を高める普遍的なWEBの品質基準です。これを機に、自社サイトをもう一度見直してみませんか?
新規WEBサイトの構築、リニューアル、アクセシビリティ対応はオーダー!におまかせください

本記事に登場したツールなどを活用して、WEBアクセシビリティの向上を目指していきましょう!