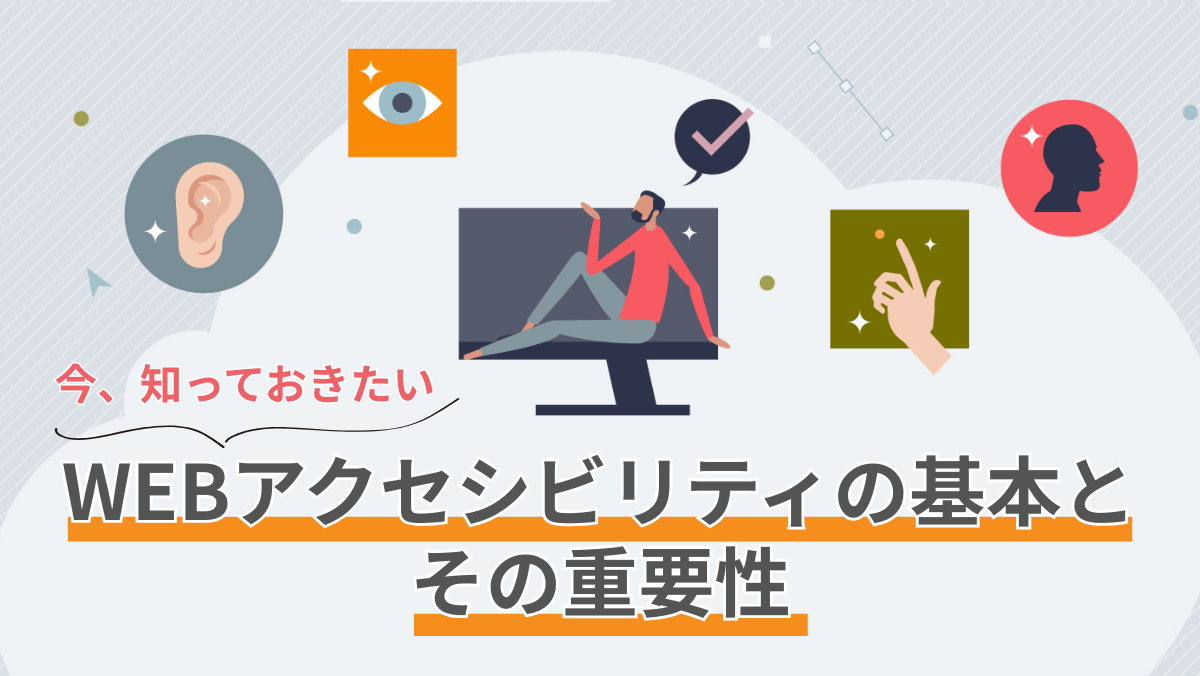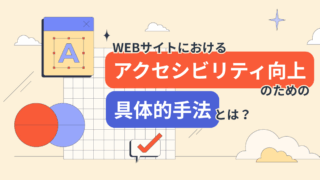インターネットは今や、情報収集、買い物、行政手続き、コミュニケーションなど、私たちの日常生活を支える欠かせない存在となっています。しかし、すべての人がこれらのサービスを同じように利用できているでしょうか。
WEBアクセシビリティとは、障害の有無や年齢、使用するデバイスや通信環境にかかわらず、誰もがウェブサイトの情報や機能に平等にアクセスできることを意味します。これは一部の人のための配慮ではなく、すべての人にとって使いやすい環境を整えるための基本的な考え方です。
2024年に施行された改正障害者差別解消法では、企業や団体に対し、WEBアクセシビリティへの合理的配慮が義務付けられました。社会全体として、情報のユニバーサルデザインが求められる時代に入ったとも言えるでしょう。
本記事では、WEBアクセシビリティの基本概念から法的背景、ガイドライン、対応によるメリットまでをわかりやすく解説します。これをきっかけに、自社サイトの改善に役立てていただければ幸いです。
WEBアクセシビリティの基本理解とその影響
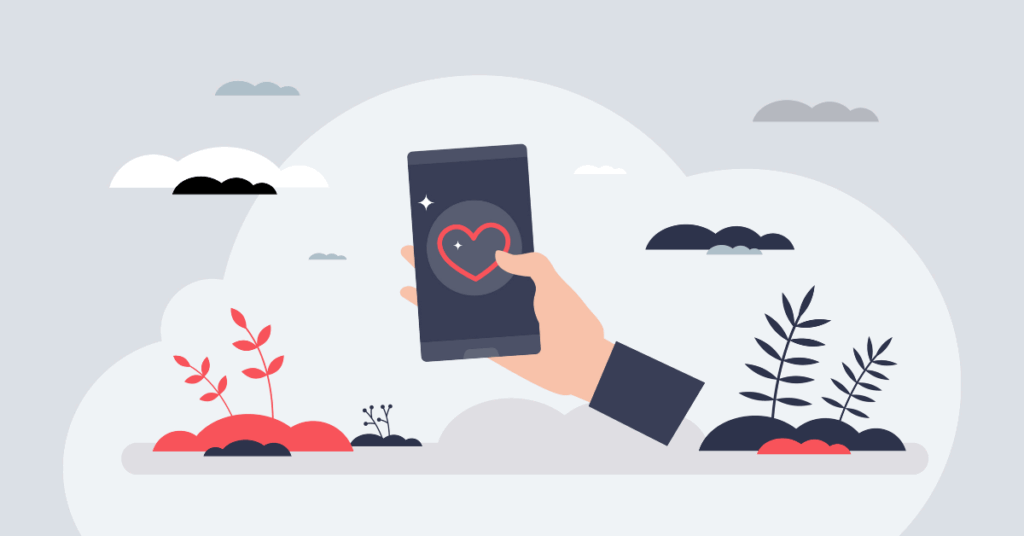
WEBアクセシビリティとは何か
WEBアクセシビリティとは、年齢、障害の有無、使用環境を問わず、すべての人がウェブサイトの情報や機能に平等にアクセスできるようにするための設計原則です。
視覚や聴覚に障害のある方だけでなく、高齢者、一時的に片手が使えない人、小さな画面で閲覧しているユーザーなど、多様な人々が対象となります。
アクセシビリティとユーザビリティの違い
WEBアクセシビリティと混同されやすい概念に「ユーザビリティ(Usability)」があります。
- アクセシビリティ:誰でも使えることに重点を置きます(例:音声読み上げ対応、キーボード操作対応)。
- ユーザビリティ:特定のユーザーにとっての使いやすさを重視します(例:直感的なナビゲーション、読みやすいフォント)。
両者は異なる視点を持ちながらも、WEBサイトの品質を支える重要な要素です。
WEBアクセシビリティが確保されている状態とは?
政府広報オンラインによると、具体的には以下のようなことが行えます。
- 目が見えなくても、情報が伝わり操作ができること
- キーボードだけで操作できること
- 一部の色が区別できなくても、情報の取得に支障がないこと
- 音声や動画のコンテンツにおいて、音が聞こえなくても内容が理解できること
※出典:政府広報オンライン「ウェブアクセシビリティとは? 分かりやすくゼロから解説!」(2023年10月)
こうした状態を実現することが、WEBアクセシビリティの本質的な目的です。
アクセシビリティが必要な理由

WEBアクセシビリティが求められる最大の理由は、誰もが公平に情報へアクセスできる社会を実現するためです。
インターネットは行政手続きや買い物、仕事、学習など、生活のあらゆる場面に関わっています。そのため、利用者の年齢や障害の有無、デバイス環境に関係なく、誰でも使えることが欠かせません。
また、たとえば片手で操作している人や、騒がしい環境でスマートフォンを見ている人、画面が小さい端末を使っている人にとっても、WEBアクセシビリティは利便性を高める要素となります。
また、2024年の改正障害者差別解消法では、企業や団体に「合理的配慮」の提供が義務付けられました(※詳細は後述)。社会全体の意識も高まりつつあり、情報やサービスの提供者には、すべての人への公平な機会の提供が求められています。
WEBアクセシビリティに関する法制度と基準
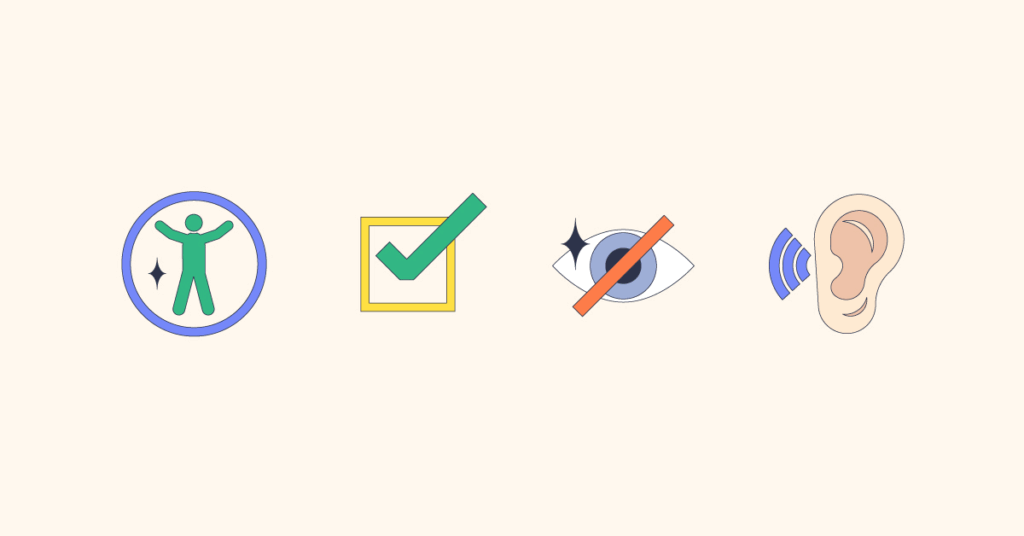
WEBアクセシビリティの取り組みは、企業の自主的な努力にとどまらず、法的にも求められる社会的責任となりつつあります。ここでは、対応が求められる法制度と、実際の設計や開発の指針となる技術的なガイドラインについて整理します。
法制度:障害者差別解消法の改正と民間企業への義務化
2024年4月に施行された改正障害者差別解消法では、これまで「努力義務」とされていた民間事業者による合理的配慮の提供が、義務化されました。これにより、WEBサイト上の情報提供やサービスにおいても、障害のある方が支障なく利用できるようにするための対応が必要になります。
合理的配慮とは?
- たとえば、視覚に障害のある方がスクリーンリーダーで操作できるようにマークアップを調整する
- 音声が聞こえにくい方のために動画に字幕を付ける
- 色覚に障害のある方でも情報が正しく伝わるように色以外の表現を併用する
など、一律の仕様ではなく、状況に応じた柔軟な対応が求められます。
この法律の改正により、民間企業も例外ではなくなったという点が極めて重要です。特にWEBを通じた情報発信やサービス提供を行う企業にとっては、対応の有無が法令遵守・リスク管理・企業イメージに直結する時代になったと言えます。
技術基準・ガイドライン:実装時の指針となる2つの基準
WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)
W3C(World Wide Web Consortium)が策定した、国際的なWEBアクセシビリティのガイドラインです。現在の最新バージョンはWCAG 2.2(2023年10月公開)で、コンテンツの perceivable(知覚可能)、operable(操作可能)、understandable(理解可能)、robust(堅牢)という4原則に基づいています。
→ WCAG公式サイト(英語)
JIS X 8341-3:2016(日本産業規格)
日本におけるWEBアクセシビリティの技術基準であり、WCAG 2.0をベースに策定されています。 国内ではこのJIS規格を基準とするのが一般的で、特に公的機関では対応が義務化されており、民間企業にも準拠が推奨されています。 実務上は、「JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAへの準拠」を一つの目標とするケースが多く見られます。
→ JIS X 8341-3:2016について|WAIC(ウェブアクセシビリティ基盤委員会)
検査・第三者評価について
日本では現時点で公式な認証制度はありませんが、JISに準拠した評価を専門業者に依頼することで、社内外にアクセシビリティ対応の姿勢を示すことができます。これは信頼性やブランド価値の向上にもつながります。
このように、法的な義務と技術的な基準の両方を理解し、それに則った対応を行うことが、現代のWEB運営においては欠かせない視点となっています。
アクセシビリティがもたらすメリット

WEBアクセシビリティへの対応は、社会的な要請であると同時に、企業やサービス提供者にとっても多くのメリットをもたらします。
主なメリット
- 利用者層の拡大
- 障害のある方や高齢者を含む、多様なユーザーが利用できるようになることで、顧客基盤が広がります。
- 売上・利益の向上
- 利用可能なユーザーが増えることで、結果として売上や利益の向上が期待できます。
- 企業イメージ・ブランド価値の向上
- アクセシビリティに配慮する姿勢は、社会的責任を果たす企業としての評価を高めます。これにより顧客からの信頼を得やすくなり、リピーターの増加にもつながります。
- 競合との差別化
- アクセシビリティ対応を進めることで、他社との差別化ポイントとしても活用できます。
考慮すべき点(デメリット)
- 初期コストの発生
- アクセシビリティ対応には、サイトの設計・改修にかかる時間や費用が必要です。
- 専門知識や人的リソースの確保
- 対応にはガイドラインや技術的な理解が求められるため、社内に知見のある人材がいない場合は外部支援が必要になることもあります。
これらのコストは短期的には負担かもしれませんが、中長期的にはユーザーの定着や企業価値向上に直結する投資と考えるべきです。
WEBアクセシビリティの基本ルール
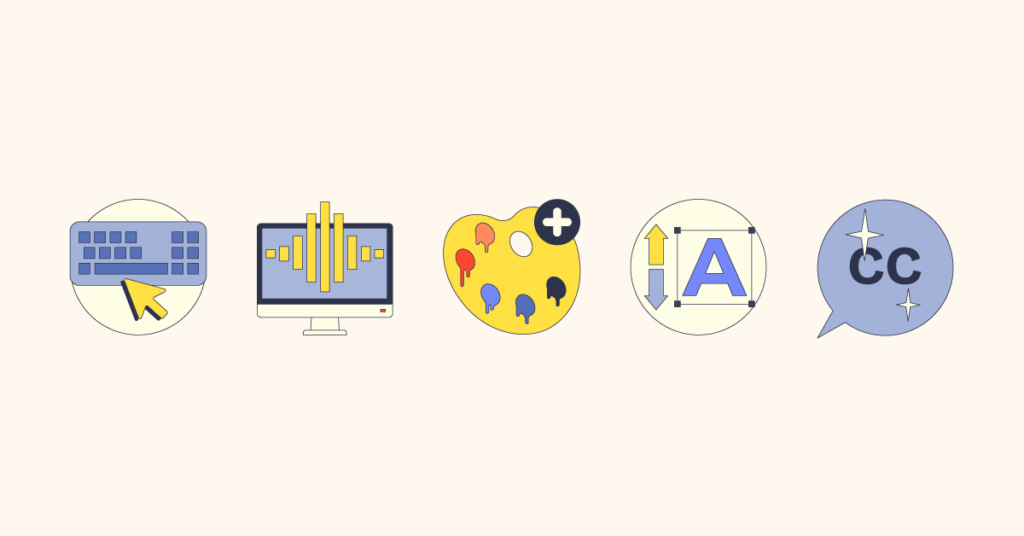
WEBアクセシビリティ対応を始めるうえで、次のような基本ルールを押さえておくとよいでしょう。
感覚に依存しない情報設計
コンテンツは視覚的な情報だけでなく、音声や触覚など他の感覚でも理解できるように設計する必要があります。たとえば、色だけで意味を伝えるのではなく、文字やアイコンなども併用して伝える工夫が求められます。
読みやすいデザイン
- 十分なコントラスト比を確保することで、色覚に障害のある方や視力の弱い方も読みやすくなります。
- フォントサイズや行間にも配慮し、目の疲れや読み飛ばしを防ぎます。
明確な構造とナビゲーション
- サイト内の情報は階層的に整理され、論理的に配置されていることが望まれます。
- 見出しやリンクは明瞭に表現され、ユーザーが目的の情報にすぐアクセスできる構成が必要です。
補助技術への対応
- 音声読み上げソフトなどの支援技術に対応するマークアップを行うことは、視覚に頼らないユーザーにとって不可欠です。
- 画像には代替テキスト(alt属性)を付与し、情報が視覚以外でも取得できるようにします。
このような基本的なルールを守ることで、誰もが公平に情報へアクセスできるWEB環境を構築することが可能になります。
なお、今回ご紹介したのはあくまで「基本編」です。より具体的な実装方法やチェックツール、実践的なデザインの工夫については、次回の記事で詳しく解説します。
<関連記事>
▼あわせて読みたい
まとめ
WEBアクセシビリティは、誰もがインターネットを快適に利用できる社会を実現するために不可欠な要素です。
法的な義務、社会的責任、そしてビジネス上のメリットの観点からも、WEBサイト運営者にとって無視できないテーマとなっています。アクセシビリティ対応には一定のコストがかかるものの、長期的には企業価値の向上、顧客満足度の向上に結びつく“投資”といえるでしょう。
今後のWEBサイト構築や改善において、ぜひWEBアクセシビリティを基盤のひとつとして取り入れていくことをおすすめします。
新規WEBサイトの構築、リニューアル、アクセシビリティ対応はオーダー!におまかせください

2024年の法改正もあって、これからWEBアクセシビリティはとても重要な概念になりますよ~