オンラインショップを運営する上で無視できない「カゴ落ち」。実際のところ、カートに商品を入れた後、約70%ものユーザーが購入手続きに進まずに離脱しています。この問題を解決するためには、具体的で効果的な施策を講じる必要があります。本記事では、カゴ落ちを防ぐための実用的な施策を徹底解説します。
カゴ落ちの現状
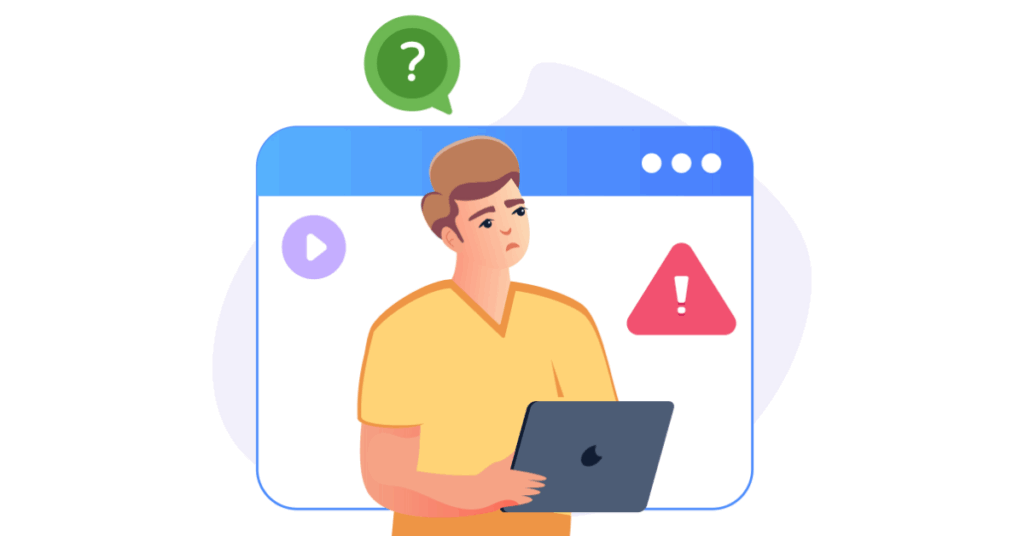
カゴ落ちとは、オンラインストアで商品をカートに入れたものの、その後の購入手続きを完了せずに離脱することを指します。
この現象はECサイト運営者にとって深刻な問題であり、実際、オンラインショップのカゴ落ち率は平均して70%を超えることも珍しくありません。この高いカゴ落ち率は、顧客の購買意欲を損ない、結果的に売上の大きな損失につながることがあります。
カゴ落ちが発生する主な原因は次の通りです。
- 隠れたコスト(送料・手数料)
- 送料やその他の手数料が決済画面で突然発生することが、顧客の購買意欲を著しく削ぐ要因です。特に、カートへ商品を入れた段階では「送料無料」とアピールしていても、購買手続き中に送料が明示されると、顧客は驚きや不快感を抱き、購入を断念することがあります。
- 複雑な購入プロセス
- 購入手続きが不必要に複雑であったり、多くの入力フォームが求められると、顧客は時間的な手間を感じて離脱する傾向があります。具体的には、以下の要因が含まれます。
- 長い入力フォームや多段階の手続き:手続きに必要なステップが多すぎると、顧客はじっくり考えることを躊躇し、結果的に購買を断念することが通常です。
- 会員登録の必要性:一部のECサイトでは、購入の前に会員登録を必須としている場合があり、これも顧客にとって大きな負担となることがあります。面倒な登録手続きや多くの情報を求められることで、顧客の意欲が削がれ、実際に購入に至らない場合が多いです。
- 購入手続きが不必要に複雑であったり、多くの入力フォームが求められると、顧客は時間的な手間を感じて離脱する傾向があります。具体的には、以下の要因が含まれます。
- 不安感(セキュリティ)
- 顧客は個人情報や決済情報の流出を恐れるため、不安を感じた瞬間に購入を躊躇します。このため、SSL証明書が導入されていない、またはサイトのセキュリティに対する疑念が残る場合、カゴ落ちの原因となります。
- 高額商品への心理的抵抗
- 高額な商品や、リピート購入を前提としない一品物に対しては、購入への心理的ハードルが高くなります。この場合、顧客はじっくりと考え、カートの中で留まったままにすることが多いため、結果的に離脱しがちです。
- 情報不足
- 商品情報が不十分であったり、商品画像や説明文が不明瞭であったりする場合、顧客は購入を思いとどまることがあります。具体的には、レビューや他の顧客の評価が見当たらない場合、信頼性に不安を持たれ、購入を後回しにされることがしばしばです。
- 競合他社との比較
- EC市場では競争が激化しており、顧客は複数のサイトを比較検討することが一般的です。他のサイトで同じ商品が安く買える場合、カート内の商品から別のサイトへと移行してしまうこともあります。
- 配達の遅れ
- 配達が遅いと感じる顧客は、購入に躊躇することがあります。特に、配達に時間がかかるとの情報があれば、顧客の購買意欲は著しく影響を受けます。迅速な配達は今日の顧客にとって期待される要素であり、在庫状況の表示や早期の配達を選べるオプションを提供することで、顧客に安心感を与えることが重要です。
- カートにメモとして入れている
- 中には、商品を後で見返すためにカートに入れた顧客もいます。この場合、顧客はその時点では購入する意図がなく、商品を一時的に保存する目的でカートに入れています。そこで、商品のリマインダーや「お気に入り」機能を提供することで、顧客に再度購入を考えさせる機会を与えることができます。
このように、さまざまな要因が重なり合っていますが、的確な対策を講じることで改善が見込まれます。
ユーザーエクスペリエンスの向上
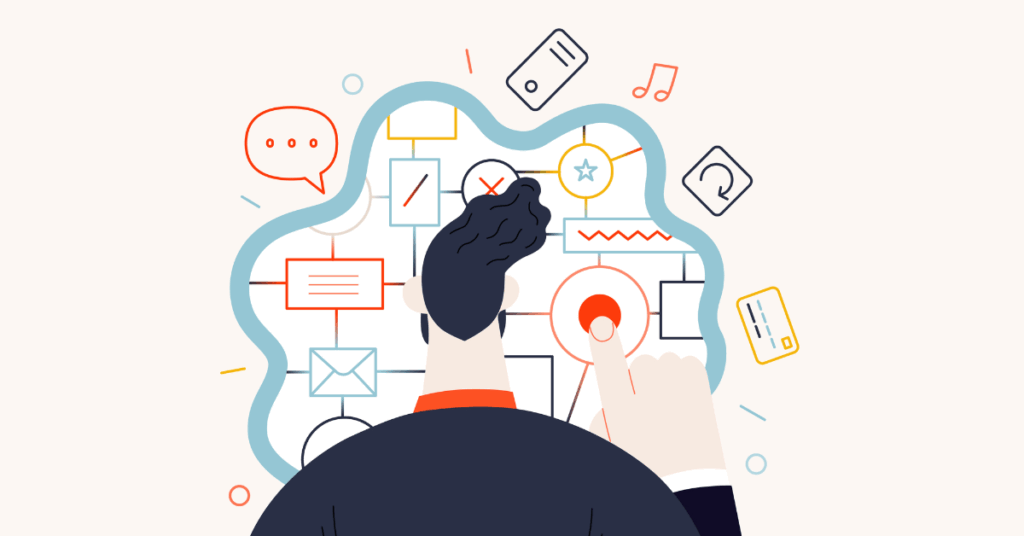
カゴ落ちにはさまざまな原因がありますが、なかでも「不便さ」や「迷い」といったユーザー体験上のストレスが大きく影響しています。
顧客が滞りなく商品の購入を進めるためには、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上が不可欠です。UXの質が高いほど、ユーザーはストレスを感じずにオンラインショッピングを楽しむことができ、結果としてカート離脱のリスクを大幅に減らすことができます。
ここでは、そうしたストレスを軽減し、スムーズな購入体験へと導くために、今すぐ見直したいUX改善の具体策をご紹介します。
デザインのクオリティ
- シンプルさの追求
- サイトデザインはシンプルかつ直感的であるべきです。わかりやすいナビゲーション、クリアな商品画像、印象的なビジュアルが効果を発揮します。
- アクセシビリティ
- 色のコントラストを適切に保ち、フォントサイズを調整することで、視覚的に優しいサイトを作ります。また、全てのユーザーがストレスなく利用できるようにするために、スマートフォンやタブレット向けのレスポンシブデザインも考慮しましょう。
送料の明確化
- 初期段階での料金明示
- 購入プロセスの初期段階で「送料がいくらかかるのか」を明確にし、隠れた費用を排除します。「おすすめ商品」のページなどでも送料無料の基準を目立たせることで、顧客が親しみを持ちやすくなります。
操作性の改善
- フィルター機能の充実
- 顧客が求める商品を簡単に見つけられるよう、商品カテゴリや価格、評価別にフィルター機能を強化します。
- サイト内検索
- 検索機能を充実させ、サジェスト機能を実装することで、ユーザーが求める商品に簡単にアクセスできるようにします。
フォローメールの効果
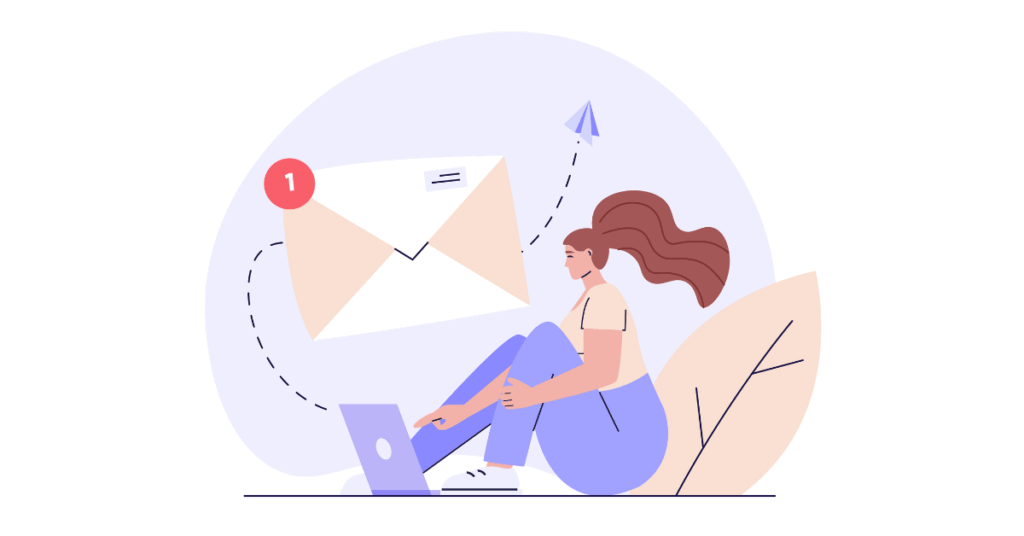
カゴ落ち後のフォローメールは、顧客に再度商品を思い出させ、購入を促すための強力なツールです。その活用方法には以下のポイントがあります。
タイミングを考えたメール配信
- リマインダーメールのタイミング
- カゴ落ちから数時間以内にリマインドメールを配信することで、訪問者の記憶に新しいうちに再興味を引くことができます。
- 段階的なアプローチ
- 3日後、1週間後に続けてメールを送信し、その中で特別オファーや割引を提案することで、購買意欲をさらに刺激します。
コンテンツの工夫
- パーソナライズされたメッセージ
- 顧客の名前やカートに入れた商品の情報を盛り込むことで、親近感を感じさせ、開封率を向上させます。
- 特別オファーの提供
- 「今だけ○○%オフ」「送料が無料に」などのオファーは、顧客の心をつかみやすくなります。急いで購入を決断させるために、期限を設けることも効果的です。
デザインとCTA
- 魅力的なビジュアル
- メール内にカートに入れた商品の画像を掲載し、購入を促進するようにします。
- 明確な行動を促すボタン
- CTA(Call to Action)は、具体的な行動を促すためのボタンを大きく、目立たせて配置します。「カートに戻る」や「今すぐ購入」といった文言が推奨されます。
決済プロセスの簡略化
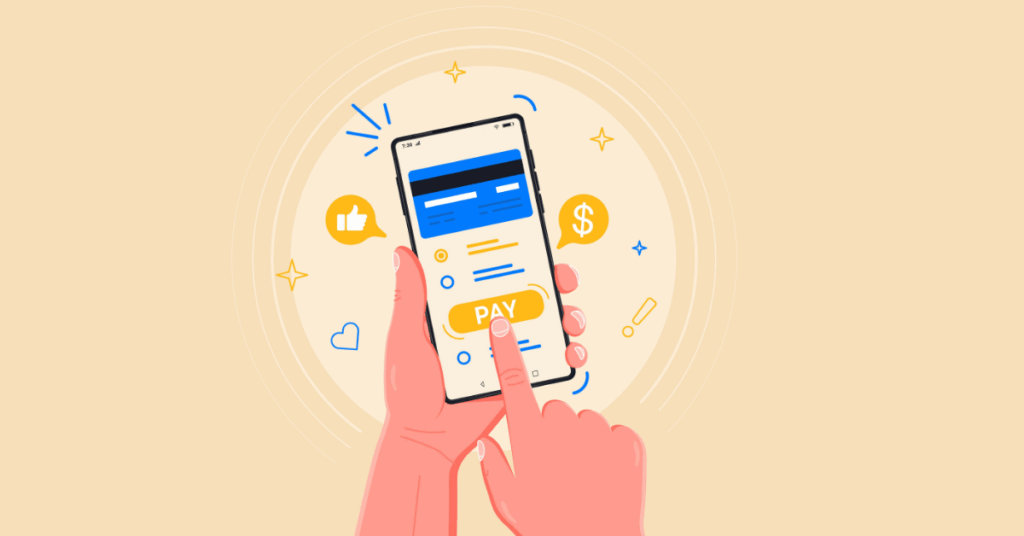
顧客の購入を円滑に進めるためには、決済プロセスの見直しが不可欠です。
ステップの簡略化
- 入力フォームの簡素化
- 不要な入力項目を削除し、必須項目だけを設けることで、顧客が感じる負担を軽減します。たとえば、電話番号を任意にすることで、より多くの顧客に購入を促すことができます。
- 一画面での購入可能
- 可能であれば、カートの中身を確認する画面から直接決済まで進められるように設定し、スムーズさを保ちます。顧客はシンプルな手続きが望ましいため、一度のアクションで進めることが理想です。
外部決済手段の活用
- 使い慣れた決済方法の導入
- ユーザーがすでに登録済みの会員情報(氏名、住所、メールアドレス、決済手段など)を利用できる外部決済サービスを導入することで、新たに情報を入力する手間を省き、購入完了までのスムーズな導線を提供します。使い慣れたアカウントでの決済が可能になるため、ユーザーのストレスを軽減し、離脱率の低下にもつながります。
リアルタイムでのエラーメッセージ表示
- 即時フィードバックの提供
- 入力内容に問題があった場合、リアルタイムで的確なエラーメッセージを表示します。これにより、顧客はすぐに自分のミスに気づき、購入手続きに戻ることができます。
セキュリティの強化

顧客が安心して購入できる環境を作るためには、セキュリティ対策が欠かせません。
SSL証明書の導入
- 情報の暗号化
- SSLを使用し、顧客の個人情報やクレジットカード情報を保護します。SSL化されたサイトは、アドレスバーに「https://」と表示され、顧客に安全性をアピールできます。
明確な運営情報の提示
- 透明性の確保
- 企業名、所在地、電話番号、プライバシーポリシーなど、運営に関連する情報をサイトの目立つ場所に設置することで、顧客に安心感を提供します。
顧客レビューや評価の表示
- 信頼性の強化
- 他の顧客からの意見やレビューを表示させることで、新規顧客にとっての信頼の基礎を築くことができます。実際の購入者の声音は、新規顧客にとっての大きな動機付けとなります。
まとめ
カゴ落ちを防ぐためには、ユーザーエクスペリエンスの向上のほか、フォローメールの活用、決済プロセスの簡略化、セキュリティの強化など、さまざまな施策を組み合わせて実施することが不可欠です。
これらのポイントを吸収し、実践することで、顧客満足度を向上させ、売上の増加を期待できるでしょう。
ECサイトの成功の裏には、顧客のニーズに応えられる仕組みや施策が必要です。ぜひ、今後の運営に役立てていただければと思います。

本記事を参考にして、カゴ落ち対策もしっかりしておいてくださいね!
